 › 沖縄の経営コンサルタント 井海のブログ › 中小企業が経営不振に陥る要因
› 沖縄の経営コンサルタント 井海のブログ › 中小企業が経営不振に陥る要因2014年08月05日
中小企業が経営不振に陥る要因
経営不振に悩む企業を建てなおすには、経営不振の根本原因を知る必要があります。
それをせずに「とにかく売上高を増やさないと」「何とか融資を受けられないか」と焦っても、結果は変わりません。
企業が苦境に陥る要因を窮境要因と言いますが、それを正しく突き止める事が大切です。
(1)経営環境への対応不足
経営環境は良くも悪くもなり、また業界構造もどんどん変化していきます。小売店の大規模化、卸の中抜き、流通行動の変化、低価格商品の普及、消費者動向の変化、県外企業の参入、デジタル化の進行、公共予算や発注基準の変化など、挙げれば切りがありません。こういった「経営環境の変化」にうまく対応できないと「時代の流れ」に取り残される形で、売上高と利益率が下がり続けます。
(2)投資の失敗
企業が成長するには設備投資や新事業立ち上げが必要ですが、見通しが甘くて期待通りの収益が得られない場合は、借入金返済や維持費に苦しむ事になります。販売力を超えた生産設備への投資、土地勘のない事業への投資、無理のある多店舗展開、本業と関係のない投資(不動産など)がその例です。財務管理ができてない企業が実力以上の投資に走ってダメージを受けるケースです。
(3)赤字部門の継続保有
赤字の事業や店舗を保持し続けると会社の資金繰りを悪化させます。部門別損益を管理していない会社に多いです。黒字部門が稼ぐ利益を赤字部門が食いつぶすため、資金繰りが厳しいだけでなく、黒字部門の競争力強化に資金を回せないため、黒字部門までやがて収益性が落ちてきます。
(4)強みを活かさない事業展開
企業が生き残るには自社の強みを最大限に活かす事業展開が絶対条件ですが、自社の強みとの関連性の薄い分野、苦手な分野で他社と勝負としている企業が多々あります。複数の事業を展開している企業の中には、自社の業種を間違って認識しているケースもあります。また、事業同士の関連性が薄く、バラバラに動いてそれぞれが他社との競争に負けているケースもあります。
(5)商品力の欠如
売上高は商品力と販売力の掛け算で決まります。そして、より重要なのは商品力です。商品力は、商品自体の魅力だけでなく、品揃え、サービス品質、技術力、供給力、価格競争力なども含みます。売上高が低下すると販売に力を入れる企業が多いですが、商品力が弱いままだと売上高は下がり続けます。売上高の低下する会社の多くは、セールスよりもマーケティングに問題があります。
(6)顧客の囲い込み不足
顧客を囲い込む仕組みがない(または弱い)会社は売上高が安定せず、常に広告費や営業人件費を掛けて新規開拓をしなければなりません。集客コストの負担が大きいだけでなく、売上高の波が大きいと固定費(作業者の人件費など)を遊ばせる事になり収益性が低くなります。
(7)新規開拓不足
顧客との継続的な取引を前提する業種では、上記とは逆に新規開拓の努力不足で売上高が低下するケースが多いです。特に、大口顧客依存の会社では、その大口客との取引が縮小すると途端に資金が回らなくなります。そもそも新規開拓の体制がなく、掛け声だけで新規開拓の取り組みが殆どなされていないケースもあります。
(8)原価管理の甘さ
商品販売や案件受注に「相場」や「他社との競争」がある以上、原価が高いと利益率が低くなり赤字体質になります。原価管理の弱い会社に多いです。原価管理をしないため原価計算の間違いに気付かず、でたらめな価格設定をしている会社もあります。また、原価を知らない営業担当者が売上欲しさに、粗利益を無視した低価格販売に走るケースもあります。
(9)高コスト体質
過去に多くの売上高を稼いでいた会社では、売上高や粗利益の低下に固定費の削減が間に合わず(または削減せず)、大きな赤字を垂れ流す傾向にあります。銀行対策で経理操作に走る会社では、更にその傾向が強く、自分で自分をごまかしている経営者もあります。また、財務体力の強化よりも節税を優先し、無駄遣いする一方で資金繰りにあくせくする会社もあります。
(10)不良資産の増加
管理の弱い会社では、売掛金の未回収や貸し倒れ、不良在庫や滞留在庫も多く、資金繰りを圧迫しています。また、取引先や知人の甘言に惑わされて貸付金や出資金などの焦げつきが発生したり、従業員の横領被害を受けたりする企業もあります。新商品開発の為に設備投資をして大量に生産したが商品が売れない、というケースもあります。
(11)社内統制の欠如
会社が組織として機能しないと、各部門や社員がバラバラに動き統制が取れなくなります。経営者と現場との距離が遠いと、現場の実情を無視した経営判断をしたり、会社方針が現場に落とし込まれず実行されなかったりします。部門間連携が弱いと、営業だけが顧客に対応する事になり、売上高も低下ます。また、仕入や生産の担当者が営業と連携しないと在庫の欠品や過剰につながります。
(12)経営管理の欠如
経営者が自社の経営状況を数字で把握していないと、経営判断を間違えたり、何をすれば良いか分からずに手を打てなかったりします。アクセル(投資)とブレーキ(節約)を踏み間違えたり、ハンドル(方向性)を切り間違えたりします。近視眼的な経営に陥る経営者も多く、方針がぶれたり中途半端な事業転換を繰り返す人もいます。
上記は全て当てはまる会社もあれば、1つだけ当てはまる会社もあります。
ただ、多くの企業は複数の要因が複雑に絡み合っています。
だからこそ、何をどうすれば良いか分からない経営者も多いのでしょう。
私が経営改善のコンサルティングに取り組む際は、こういった原因分析を徹底的に行います。
そして、その企業が経営不振に陥った本当の原因を浮かび上がらせた上で、経営改善の方向性を見出します。
自社の経営不振(業績悪化や資金繰り悪化)にお悩みの経営者は、是非ご連絡下さい。
それをせずに「とにかく売上高を増やさないと」「何とか融資を受けられないか」と焦っても、結果は変わりません。
企業が苦境に陥る要因を窮境要因と言いますが、それを正しく突き止める事が大切です。
(1)経営環境への対応不足
経営環境は良くも悪くもなり、また業界構造もどんどん変化していきます。小売店の大規模化、卸の中抜き、流通行動の変化、低価格商品の普及、消費者動向の変化、県外企業の参入、デジタル化の進行、公共予算や発注基準の変化など、挙げれば切りがありません。こういった「経営環境の変化」にうまく対応できないと「時代の流れ」に取り残される形で、売上高と利益率が下がり続けます。
(2)投資の失敗
企業が成長するには設備投資や新事業立ち上げが必要ですが、見通しが甘くて期待通りの収益が得られない場合は、借入金返済や維持費に苦しむ事になります。販売力を超えた生産設備への投資、土地勘のない事業への投資、無理のある多店舗展開、本業と関係のない投資(不動産など)がその例です。財務管理ができてない企業が実力以上の投資に走ってダメージを受けるケースです。
(3)赤字部門の継続保有
赤字の事業や店舗を保持し続けると会社の資金繰りを悪化させます。部門別損益を管理していない会社に多いです。黒字部門が稼ぐ利益を赤字部門が食いつぶすため、資金繰りが厳しいだけでなく、黒字部門の競争力強化に資金を回せないため、黒字部門までやがて収益性が落ちてきます。
(4)強みを活かさない事業展開
企業が生き残るには自社の強みを最大限に活かす事業展開が絶対条件ですが、自社の強みとの関連性の薄い分野、苦手な分野で他社と勝負としている企業が多々あります。複数の事業を展開している企業の中には、自社の業種を間違って認識しているケースもあります。また、事業同士の関連性が薄く、バラバラに動いてそれぞれが他社との競争に負けているケースもあります。
(5)商品力の欠如
売上高は商品力と販売力の掛け算で決まります。そして、より重要なのは商品力です。商品力は、商品自体の魅力だけでなく、品揃え、サービス品質、技術力、供給力、価格競争力なども含みます。売上高が低下すると販売に力を入れる企業が多いですが、商品力が弱いままだと売上高は下がり続けます。売上高の低下する会社の多くは、セールスよりもマーケティングに問題があります。
(6)顧客の囲い込み不足
顧客を囲い込む仕組みがない(または弱い)会社は売上高が安定せず、常に広告費や営業人件費を掛けて新規開拓をしなければなりません。集客コストの負担が大きいだけでなく、売上高の波が大きいと固定費(作業者の人件費など)を遊ばせる事になり収益性が低くなります。
(7)新規開拓不足
顧客との継続的な取引を前提する業種では、上記とは逆に新規開拓の努力不足で売上高が低下するケースが多いです。特に、大口顧客依存の会社では、その大口客との取引が縮小すると途端に資金が回らなくなります。そもそも新規開拓の体制がなく、掛け声だけで新規開拓の取り組みが殆どなされていないケースもあります。
(8)原価管理の甘さ
商品販売や案件受注に「相場」や「他社との競争」がある以上、原価が高いと利益率が低くなり赤字体質になります。原価管理の弱い会社に多いです。原価管理をしないため原価計算の間違いに気付かず、でたらめな価格設定をしている会社もあります。また、原価を知らない営業担当者が売上欲しさに、粗利益を無視した低価格販売に走るケースもあります。
(9)高コスト体質
過去に多くの売上高を稼いでいた会社では、売上高や粗利益の低下に固定費の削減が間に合わず(または削減せず)、大きな赤字を垂れ流す傾向にあります。銀行対策で経理操作に走る会社では、更にその傾向が強く、自分で自分をごまかしている経営者もあります。また、財務体力の強化よりも節税を優先し、無駄遣いする一方で資金繰りにあくせくする会社もあります。
(10)不良資産の増加
管理の弱い会社では、売掛金の未回収や貸し倒れ、不良在庫や滞留在庫も多く、資金繰りを圧迫しています。また、取引先や知人の甘言に惑わされて貸付金や出資金などの焦げつきが発生したり、従業員の横領被害を受けたりする企業もあります。新商品開発の為に設備投資をして大量に生産したが商品が売れない、というケースもあります。
(11)社内統制の欠如
会社が組織として機能しないと、各部門や社員がバラバラに動き統制が取れなくなります。経営者と現場との距離が遠いと、現場の実情を無視した経営判断をしたり、会社方針が現場に落とし込まれず実行されなかったりします。部門間連携が弱いと、営業だけが顧客に対応する事になり、売上高も低下ます。また、仕入や生産の担当者が営業と連携しないと在庫の欠品や過剰につながります。
(12)経営管理の欠如
経営者が自社の経営状況を数字で把握していないと、経営判断を間違えたり、何をすれば良いか分からずに手を打てなかったりします。アクセル(投資)とブレーキ(節約)を踏み間違えたり、ハンドル(方向性)を切り間違えたりします。近視眼的な経営に陥る経営者も多く、方針がぶれたり中途半端な事業転換を繰り返す人もいます。
上記は全て当てはまる会社もあれば、1つだけ当てはまる会社もあります。
ただ、多くの企業は複数の要因が複雑に絡み合っています。
だからこそ、何をどうすれば良いか分からない経営者も多いのでしょう。
私が経営改善のコンサルティングに取り組む際は、こういった原因分析を徹底的に行います。
そして、その企業が経営不振に陥った本当の原因を浮かび上がらせた上で、経営改善の方向性を見出します。
自社の経営不振(業績悪化や資金繰り悪化)にお悩みの経営者は、是非ご連絡下さい。
Posted by ikai at 15:26│Comments(0)




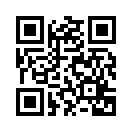
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。